
Future2025巻頭インタビュー
哲学者 谷川嘉浩さん①
計画性や将来設計は大切とされます。
しかし、「なんとなく」の衝動を見逃さずに進むと、予想外の新しい景色が広がるかもしれません。
気鋭の哲学者、谷川嘉浩さんが将来を豊かに変えてしまう衝動の見つけ方を教えてくれました。
「なんとなく」から広がる世界
◇高校時代の谷川さんは、どんな高校生でしたか?
部活も恋愛も一生懸命でしたよ。吹奏楽部でトロンボーンを担当していて、二つ上の先輩と付き合っていました。高校生らしい毎日で当時はまだ”哲学“なんて言葉も自分からは遠かったです。
勉強は正直それほどでもありませんでした。暗記が嫌いだったので公式を覚えさせる教え方だった数学が当初特に苦手でした。そうは言ってもやらないといけないので、数学については友だちに「丸一日私の質問に付き合って」とお願いして、夏休みのマクドナルドで教えてもらいました。おかげさまで数学はむしろ得意になりました。
◇そもそも哲学者とは、何をする人なのでしょうか?
「哲学は万学の祖」と言われる通り、昔はあらゆる学問が”哲学“の大きな枠組みの中にありました。しかし、科学や心理学などが分野として独立していきます。その結果、”残りかす“的に残った部分が今の哲学だと説明されることがあります。
ただ、言い換えれば「世の中の役に立つか、立たないか」の枠からこぼれ落ちたものを拾い上げ、考え続けるのが哲学者とも言えますね。
現代の哲学は最終的にはいろんな学問や社会システムと接続する”余白“の場所でもあります。たとえば、医療や情報テクノロジーの倫理、SNSやAIがもたらす人間観の変化など、これまでの方法で処理できない話題は突き詰めると哲学の問いに行き着く。そういう「必要そうだけど、今は必要じゃない。でもこれから必要になるかも」ということを、ずっとああでもないこうでもないと考え続けるのが哲学者だと思います。
自分を決め打ちしない
◇進路はどのように決めたらいいですか。
高校生が将来を考える時、「自分の思いや状況はずっと変わらない」という前提に立ちがちなんですね。未来から逆算して人生を計画し、作業のように生きようとしてしまう。でも、人は変わります。中学でテニスをやっていても、高校で弓道をやる人がいるでしょう?小さい頃に花屋になりたいと言っていても、数学者になることだってあります。それでいいんです。変化して当然なんです。人の好き嫌いや環境は変わり続ける。得意なことの内容が変わったり、今の興味が薄れたりするし、将来の自分が予期せぬ出会いで別人のようになるかもしれない。
キャリアデザイン(※将来の働き方や生き方をあらかじめ設計する考え方)という言葉がありますが、それは自分自身が変化する可能性を抑圧したところに成立する考え方でもあります。
10代の知識や経験なんて限りがありますよ。憧れている業界や大学のイメージは、大抵「外から見て感じたイメージ」にすぎません。実際に飛び込んでみたら「思ってたのと違う」なんてことは山ほどある。あらかじめ下調べしても、自分がどう感じるかまでは分かりませんよね。
それなのに「本当の自分はこう」と決め打ちしてしまうと、現実と違ったときのギャップがすごくつらい。あるいは、「違う」と思っていても自分を無理に合わせちゃう。そんな風に自分を追い込んでしまうのは、もったいないと思います。
谷川 嘉浩
哲学者

たにがわ よしひろ/哲学者。1990年生まれ。京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師を務めている。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程を修了。近著には『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(ディスカバートゥエンティワン)や『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』(ちくまプリマー新書)がある。
※掲載内容とプロフィール情報はFuture 2025[進学・オシゴト版]2025.3.12時点のものです。

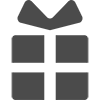 プレゼント
プレゼント webun
webun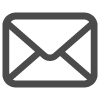 お問い合わせ
お問い合わせ