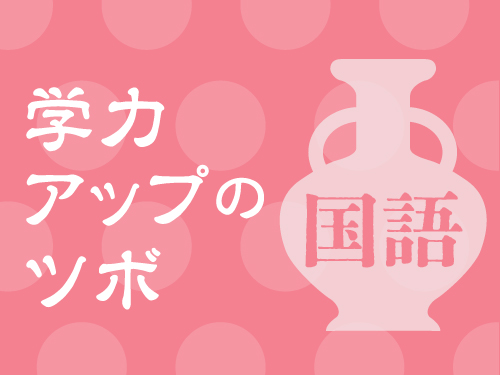
学力アップのツボ(国語)
Future vol.19掲載
普段何げなく使っている日本語も、いざ国語科目となると苦手意識を持っている人も多いのでは?
学びのコツをつかんで、読解力や思考力、意思伝達力を身に付け、言葉の力で未来を開こう!
【現代文】「読み解く力」と「伝える力」を付けよう
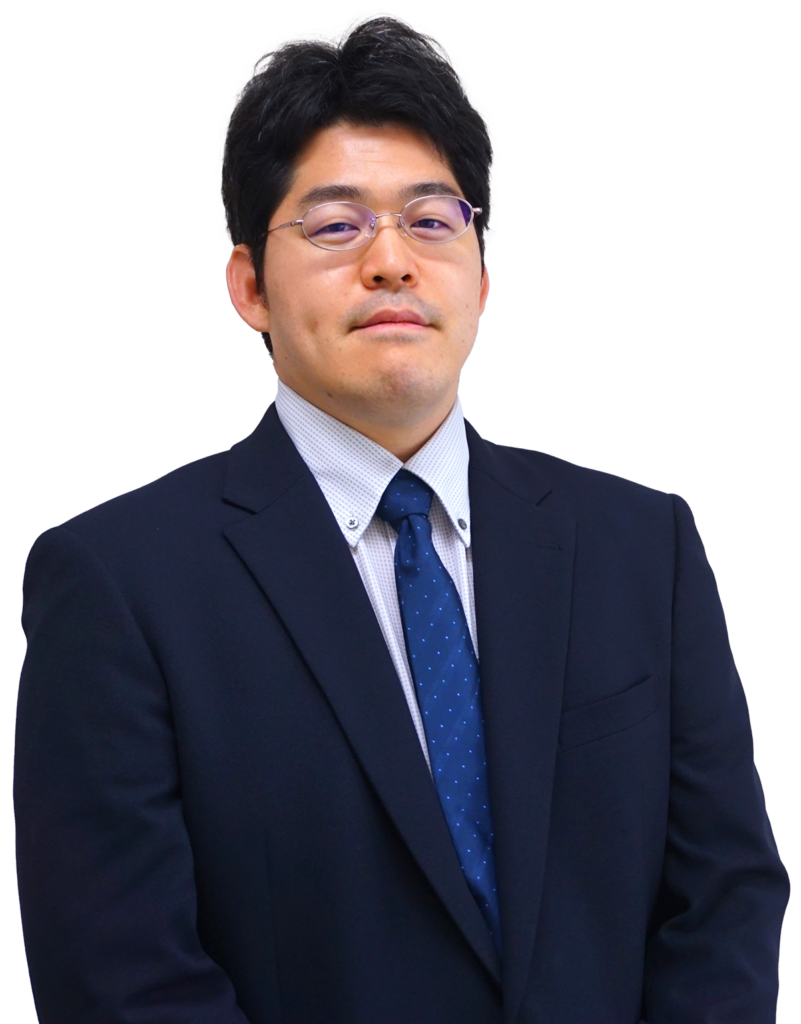
現代文は、筆者が書いた文章を読み取り、第三者(出題者)に報告する科目です。自分の感想や価値観などを交えず、とにかく本文の記述に厳格であること。記述説明では本文をそのまま引用しても良いですが、内容を知らない相手にも同程度の理解を得られるよう、全体の趣旨や周辺の文脈を踏まえ、内容を補強したり表現を言い換えたりする工夫が必要です。
評論の読解では、筆者の批判的思考を意識するのが大切です。批判的思考とは、物事に課題を見出し、その解決に向けて考えることです。評論は、社会の諸事象や人々の認識に対して、筆者が感じた問題点・疑問点を動機として書かれています。主張や結論(ゴール)ばかり意識せず、課題意識(スタート)にも目を向けましょう。「スタート」を読み取ることができれば、「ゴール」もつかみやすくなります。課題意識は文章冒頭付近に書かれることが多いので、読み終えた後に改めて冒頭を読み直すことも効果的です。
現代文が苦手な人は、実は語彙力や知識不足が原因であることが多いです。国語学習だけでなく日常のさまざまな言語活動を通して豊かな言葉の力や幅広い教養を育み、学力アップを目指してください。
ポイント
①現代文は本文の記述に厳格であれ!
②評論の読解では筆者の課題意識にも目を向けよう。
Q. 国語にハマったきっかけは?
A. 大学で学んだ日本の中古文学です。時代を超えても、人々の感情や価値観は現代に通ずるものがあるのだという面白さに気が付きました。
【小論文】読む、考える、書くを繰り返す

小論文は相手を説得するための文章です。作文と違い、根拠を示し、自分の意見を論じるためには知識がないと書けません。そこで、日頃から本や新聞を読む習慣をつけることが大切です。最近は本離れが進み、長文を苦手とする人が増えていますが、興味のある分野から始めてみましょう。図書館で司書さんに本を紹介してもらう、タイトルに引かれた本を手に取ってみるのも良い方法です。読破する必要はなく、気になる部分だけでもよいので文章を読んで情報や知識をインプットすることが大事です。
インプットと同じくらい重要なのが「書く練習」です。小論文ではいくら文章が上手でも、論点が外れていては意味がありません。基本的な文章構成である「起承転結」を身に付け、そこから自分なりの文章の「型」を作りましょう。「型」があればどんな課題にも応用が利きます。小論文を書く時は、まず課題文をしっかり読解し、どのような流れでどう自分の意見を盛り込むか下書きをすると頭の中が整理され、一貫性のある文章が書けます。
小論文は自分の言葉で書くことに意味があります。初めは拙い文章でも、「読む」、「考える」、「書く」を繰り返すことで上達します。ぜひ実践してみてください。
ポイント
①普段から本や新聞を読もう!
②自分なりの文章構成の「型」を身に付ける。
Q. 国語教諭になるきっかけは?
A. 本や書道が好きで、好きなことを生かせる仕事に就きたいと思ったからです。
【古典】古典は生きた人間を描いた物語。登場人物の世界を追体験しよう!

皆さんの中には、大河ドラマ「光る君へ」をきっかけに古典の面白さに開眼したという人もいるかもしれません。古文では難しく感じる内容も、映像にすると一気に身近に感じられます。古典学習も同じで、文法や単語だけにとらわれず、物語を頭の中でイメージできるかどうかが大事です。まずは古典をモチーフにした漫画や現代小説で物語の全体像を捉え、それから原文に挑戦するのもよいでしょう。古典は、長い年月を越えて読み継がれてきた「生きた人間を描いた物語」です。登場人物に着目し、現代とは異なる感性や人間の普遍的な感情を読み取れると、より理解が深まりグッと面白くなります。
物語の内容が理解できたら、次は声に出して読んでみましょう。古文は、音の響きやリズムが現代文とは異なるため、音読によるアウトプット学習が効果的です。原文、訳文を交互に読むことで、文法や単語がどのように使われているかも学べます。何度も声に出して読み、当時の“生きた言葉”に触れてみてください。
古典は、何百人、何千人の物語を追体験できる面白い学問です。現代の暮らしに役立つ生き方や考え方も隠れているので、自分自身と重ね合わせながら楽しく学びましょう。
ポイント
①物語を頭の中でイメージ化しよう!
②アウトプットでさらに上達!声に出して生きた文法・単語を学ぼう。
Q. 古典が好きになったきっかけは?
A. 源氏物語が大好きな恩師の影響を受けて訳文を読み、私も古典の魅力にハマってしまいました。
※掲載内容はFuture vol.19(2024.11.11)時点のものです。

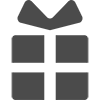 プレゼント
プレゼント webun
webun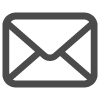 お問い合わせ
お問い合わせ